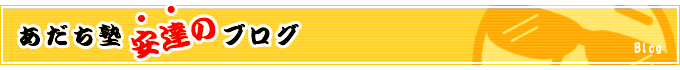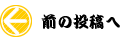彼岸と此岸
2013年04月03日
願わくは花の下にて春死なん そのきさらぎの望月の頃
西行
「願わくは2月(旧暦)の満月の頃、満開の桜の下で死にたいものだ」
平安の昔から日本人は咲き誇ってははかなく散る桜に美を見出してきました。上の西行の歌も桜の美しさと死のイメージが結びついています。
梶井基次郎の小説「櫻の樹の下には」は「桜の樹の下には死体が埋まってゐる!」で始まります。初めて読んだとき、衝撃を受けました。
あまりにも実感できるイメージだったからです。それほど桜には「あの世とこの世(彼岸と此岸)」、「生命と死」というイメージに容易に結びつく特別な美しさがあるように思います。
実際、前の戦争中では「お国のために花と散る」など、戦争による死を美化するものとして利用されもしました。
このためでしょうか、安部公房(作家)にとっては、花びら一枚では白にしか見えないが、全体では煙るように淡くピンクに見えるあの桜の美しさは「人に何か正常な判断を失わせてしまうような不安」を抱かせるものとして映ったようです。
僕も桜の美しさから「終わりと始まりの間の静止した時」を感じます。「生」でも「死」でもない止まったような世界に身を置くとき、毎年このようなことを思います。

そして桜の季節が終わると、もう一度生まれたような気がして元気になります。

こんな風景がある斑鳩町はいいところだと思います。
堀居