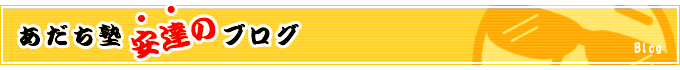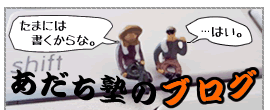Newest post - date : 2014年4月17日
中二Bクラスの授業後の小テストがありました。できるまで何度でも採点してはやり直し。
比較的すんなりと合格して帰る生徒もいれば、悪戦苦闘して長期滞在になる生徒もいます。
学力とひとくくりに言いますが、正解を一発で出すという能力よりも、間違いを探して正しく修正する能力の方がはるかに高級です。知識がきっちりと構造化されて、順序立てた考えをしないといけないからです。
僕も○×だけつけて答案をつっ返すようなことはしません。その生徒に応じたちょっとしたヒントは述べます。しかし手を出しすぎてはいけない。手とり足取りこちらの言うままに正解にたどり着いても、次回にはすっかり初期化されて何も残っていません。
ただ、放っておくとすっかりフリーズしてしまう生徒もいます。ここまで来ると一つずつ順を追って答えにたどり着かせようとします。ところがここでも難航。目的地へたどりつくどころかすっかり漂流状態になったりします。
気がつけば11;30。あと二問だけなんだから、とこちらは必死で説明。これがいけない。こっちがあせっても結局無理やり答えにたどり着かせただけになってしまいました。
反省しきりです。次改めて補習しましょう。
こっちがあせってはいかんのです。
date : 2014年4月16日
中三英語、現在完了「継続」に突入。導入はまず成功しました。現在完了は日本語の概念にない用法なので導入時の概念理解が肝です。なかなか興味を持って解説を聞いてくれます。特に中三Bクラス。単語テストも全員が満点で合格。すばらしい!Aクラスも全員合格はしていますが、気を抜かないように。 さて、それはさておき... 続きを読む
date : 2014年4月15日
先日中三で受動態の達成度テストをしました。採点をして結果を張り出しました。一定点数以下は補習。一人ひとりコメント入りです。 生徒が来ると様々な反応が。「いや~!補習いやや~」、「おれセーフや!」、「なんで・・・結構できたと思ったのにイ」、「お、おまえ補習やんけ!『撃沈』て書かれているやんケケッ、・・... 続きを読む
date : 2014年4月12日
中二Aクラス。 ガンガンいっています。 現在-過去時制はBeも含め、混合問題の総まとめが終わろうとしています。 難易度の高いレベルで高い正答率が出てくるようになりました。時制の見分けをしつこく練習するのは、これが受験までの英語の根本的な土台になる部分だからです。 ここを曖昧にしたままで次の単元を上乗... 続きを読む
date : 2014年4月11日
四月は塾講師は比較的時間に余裕が生まれる。私と堀居はこの短い春を数週間週休2日なるものを体験できる。 私は来る9月のために、その日をトレーニングにあてている。日ごろ出来ない距離を足に刻んでいる。 この火曜日も通常の2倍の距離を刻んでみたが、笑えるほど走れない。ついに25㎞地点で足が動かなくなり残りの... 続きを読む
date : 2014年4月9日
H:はい、授業するで~。宿題のプリント出して~ 生徒:・・・プリント失くした・・・ H:はあ!?はよ言わんかい!ん~しゃあないなあ、今はこの予備のプリント持って・・・ 生徒:・・・でも見つけて宿題やってきた。 H:???へ?ほんならプリント失くしたって言わんでいいやんけ!もう、紛らわしい! さて、こ... 続きを読む
date : 2014年4月8日
今日第一期卒業生の多くがあだち塾に集まって短い時間を過ごしました。 ただまったりと二時間ばかり過ごしただけなのですが、おそらくこの面子で集合するのは今回が最後になると思うと、ついこの間まで目の色を変えて必死で勉強していた生徒たちの、本来の姿が見えて興味深かったです。観察記録は別の機会にでも(笑)。 ... 続きを読む
date : 2014年4月6日
この雨で桜も散ってしまいそうです。今年はあのうっとりする気分には浸れないかもしれません。 ところで桜前線などのことばで表される桜は、数ある桜の品種のなかでも「ソメイヨシノ」といわれるものです。 この「ソメイヨシノ」、江戸時代の江戸は染井村で、二品種の掛け合わせからうまれた人工的な改良種です。病害虫に... 続きを読む
date : 2014年4月5日
本日の中二の授業。 Aクラスはbe動詞の過去形に突入しました。いいペースです。過去時制全般は一つ一つは理解できても現在形、過去形、一般動詞、be動詞を総合的に出題されると必ずまた混乱します。覚えた不規則変化動詞もすぐ忘れますし。しかしここは英語の中で根幹を成す部分です。未来形に入る前にもう一度総復習... 続きを読む
date : 2014年4月4日
さて本日の中三国語の授業で読んだ問題。解説はよく理解してくれたみたいです。 本文の内容の半分は著者福島真一(分子生物学者)の「生物と無生物のあいだ」で詳しく述べられています。興味があれば読んでみるといいですよ。そんなに難しいことが書かれているわけではありません。中学生でも充分理解できます。 「分子レ... 続きを読む